
金峰山探訪記(2)
Tweet
訪問日 2019/11/24
2020/06/02 投稿
随分と遅い更新だと自分でも思う。そんな方がおられるのかどうか分からないが、お待ち頂いた方にはただただ陳謝するばかりです。
役所や医院の手続きで、色々と動く事が出来て、ばてて倒れて、机に向かう気力が無かったのです。
又、老化が進んでいるのか? 執筆スピードが驚く程落ちて来ているのも遅れた理由の一つです。 まぁ、何を言っても言い訳にしかなりません。。本題へ再開へと参りましょう。
ここから本題です。
まずは境内を和らげる、ミストとマイナスイオンですが、古い水請いの神社をたくさん回って、その仕掛けに気づきました。
水流や泉の上に、赤子の頭位の大きさ球形の石をうず高く置いて整地するのです。
普通は五メートル程、積み上げますが、ここ金峰山の境内は2、30メートル程積み上げています。
水流は浸透圧で境内全体まで吸い上げられて、ミストとなります。
その労力は想像を絶します。
それにその手の神社は大抵、人里離れた難所にあり。球形の石などどこにも無いのです。信じがたい事ですが、球形の岩をぽろぽろと生み出す場所や、球形の岩が川の様に並んでいる場所は知っていますが、そこから運んで来たとと言うのは突飛にすぎるでしょう。
私には、この球形の岩は謎です。
積み上げるだけでも、大変な労力なのに、まさか岩を削ったとは思えない。
本当に謎です。
パンフレットを見ると、石段を400段下りた所に、「脳天大神」と言う社があり、滝行も座禅も出来る施設があります。
ミッチーさんが、ここが千日回峰の出発地点だと教えてくれました。400段の階段を上り下りする体力は私にはありません。
それどころか、元来た道を戻っただけで息が切れ、売店の長椅子でへたり込みました。
ミッチーさんは水分(みまくり)神社へ行きたいと言います。関東ではパワースポットとして名高いそうです。
水分神社と言えば、私は大阪から二上山行く河内側にあるものしか知りません。
そこは急な坂にあるせいで、駐車場も無く、、入り口も狭いですが、中は広く、芝生の緑が美しい場所で、近所の方の散歩場所になっていました。
私が聞いた話では、水争いの際に楠木正成が、この場所で仲裁したので、水分神社と言い、最新も正成だと言います。
私がその話をすると、ミッチーさんは首を傾げます。
子安神社とも言うのですがとミッチーさんは言います。子種神社なら知っていますが、関西に永らく暮らして、その名を聞いたことがありません。
パンフレットだと、子安神社は歩いて行ける距離にある様に見えます。ミッチーさんは急な坂のカーブを曲がって姿を消します。子安神社が見えないか探りに行ったのでしょう。
私は甘味処のベンチに腰を掛けて待ちます。何故か息が上がっていました。
戻って来たミッチーさんは、そんな私の様子を見て、「歩けます?」と聞きます。「この坂を? 多分、無理です」我ながら情けない返事を返します。
ミッチーさんは甘味処の老夫妻にTAXIが呼べるか尋ねます。三台しかないけど、今は二台空いている筈だとの答えが返って来ます。
三台しかない? それで観光が回るのかと思いました。
TAXIは直ぐに来ました。
「近くて悪いのですが、子安神社までお願い出来ますか?」と言うミッチーさんの問いに、初老の運転手は「近くないよ。歩けば半日かかるぞ」と答えます。
「このパンフレット、詐欺やん!」ミッチーさんと私がハモります。
「対向車が来たらどうにもならんから、遠回りやけど広い道行っていいかな?」運転手さんの問いに、「どうぞどうぞ」と私とミッチーさんは答えます。奈良の山中の酷道は熟知している二人です。
TAXIは急カーブのキツイ坂道を登ります。エンジンが苦しい声を上げています。
「こんな坂、オレの車やったら登られへん」
そうこぼすと、運転手さんは「冬はチェーン巻いても登られへんで。そやからっこれからの季節、なんも仕事が無くなるんや」と言われます。都会に出ず、この地に残る事の生活の苦しみが篭もった言葉でした。
同時にそんな環境下で千日回峰へ挑む方への、畏怖と畏敬を感じました。
TAXIは厳しい坂道を登ります。ブラインドコーナーが続きます。ガードレールはあります。でも、延々とTAXI一台分の車幅しかありません。
「「これが広い道なんですか? 対向車避ける所もありませんやん!」と叫んだら、運転手さんは皆まで言うなと言う顔で笑います。登り切った所で、運転手さんは車を止めました。ここならすれ違いは可能です。
「ここからの見晴らしが一番綺麗なんや。あの下はみんな桜で、カメラマンはここから写真を撮るんや」
「もしかして中千本ですか?」
運転手さんは自慢げに頷きました。
地元の方にも誇りの場所だと分かりました。
| ちなみにTAXIの位置から観た春の中千本 です。下の峠道です。 |
 |
そこから急な斜面を下って、細い道を右折すると小さな門があります。なにやら賑わっていました。下から来たもう一台のTAXI。そして私たちを抜かして行った老人と孫とその家族。車中から見ると女の子は笑っています。
正直、ぞっとしました。山に慣れた者でも苦労するで在ろう斜面をTAXIを使って来た私達と同時に登って来ているのです。同じ人間とは思えませんでした。
TAXI二台は目で合図して距離を取り合い、停車しました。流石は地元の同業者。どちらも難無く発車出来る位置取りが出来ています。
もう一台のTAXIからは初老のご婦人方が乗っていました。観光客然とした方々でなんだか安心しました。
さて、門の入り口では皆さん譲り合って、人だまりが出来ましたが、グループとしては最年少の私とミッチーさんは、示し合わすことも無く、門の尾左脇にどいて、皆さんが入るのを待っていました。
実を言うと私は(なんだ? ここは? 神社? 寺? 違う! それにあれはなんだ?)と門を入って右の神体山を睨んでいました。その圧倒的な気配と山裾で私達を見て構えている何百と言う異形達に警戒の念を抱いていました。ミッチーさんも気配には気づいているようで、固い視線を山へ向けていました。
山門を潜った私は違和感に囚われました。(鳥居は無いのか?) 鳥居の携帯で祀られる神を類推出来るのに……
後日、ミッチーさんに確認すると、鳥居は門と密接する形であったとのこと。
この私が鳥居をセンサーから見逃すとは不覚です。
敷地内に入った私は、それこそ心中で叫んでいました。
(何じゃあ! ここは!?)
確かに聖地だ! だが、天孫降臨以前にすでにあった場所だ。そもそも、人を相手にしていない。人がゴキブリが部屋に入ると嫌悪感を抱く様に、山の気配は我々を汚れとして、出て行けと思念を送ってくる。
境内は門から入ると長方形に奥に広がる形で、私は他にこんな造りは見たことも無い。
山がご神体の筈だが、山側は造りを施した板塀になっている。
| こんな感じだ。 これでは神様が何体いるのか分からないし、当然の様に表示もまるで無い。 |
 |
| しめ縄の内側はこうである。 |
 |
これじゃ、どちら様か分からない。ただ、こちら側は手入れが良く入っていて大事にされている。正面と長い左サイドが続いているが、左サイドは一カ所を除いて、屋根のある吹き抜けで置かれている物は風雨に晒され、右再度とは雲泥の違いである。境内も中央付近に三つの土台があり、用途も分からない。ただこの所為で狭い境内が益々狭くなっている。
正面は流石にちゃんとしているが、なんかとってつけた様で騙されてる感が半端無い。
| 正面の様子。 |
 |
大体、左サイドでこんな種明かしをしている。
 |
| これが本物の子安神だろう。気配も半端無い。 |
左サイドには幾つか興味を引くものがあるが、個人的にはこの部屋が気になる。
 |
| 私のカメラには手ぶれ補正機能があるので、普通、こうは写らない霊波動が尋常ではない時、こう写る。 |
そして、神社なら神輿は宝物庫に入れて大事に保管する。当然だ。神輿は神の依代で神社の威風を示すものだが、ここでは左側の床に放置され、風雨に晒されている。
だが、私がその神輿に抱いた感想は、本当にこれを祭りに使ったのかと言う疑問だ。
施されている文様は古代遺跡にも見られるし、この扱いは神輿へのものではない。
聖櫃(アーク)としか思えないのだ。
 |
神社にあって然るべきもので、安心した物も放置されていた。
 |
古い神社には良くあるもので、太陽信仰を示すもので、この御簾の奥には太陽神の巫女が控えるものだ。飾ってある幾つかの絵から、物語を読み取りたいが、分からないものは仕方がない。
| これも神社の神話を神楽として奉納されたものだろうが、神楽は廃れたのだろう。剣呑な神楽だったようだが。 |
 |
| わざわざ飾られるこの方は誰? なんで、顔を削られているの?(。>_<。) |
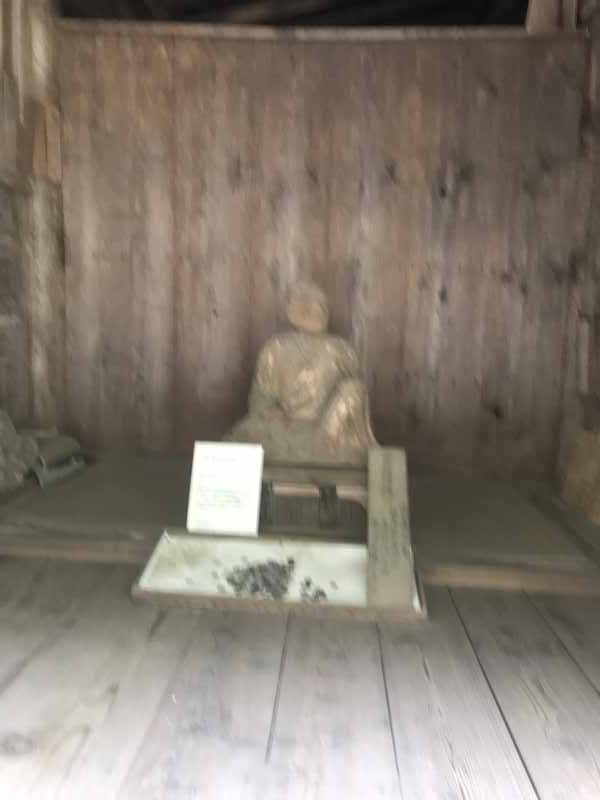 |
| 神主の趣味? なんでチェーンソー彫刻? 神社へ置く意味あるの? |
 |
と言う訳で子安神社はパワースポットではあるが、常人が入る場所じゃないと痛感した。
それでも私はミッチーさんに尋ねた。
「ここで夜を明かしたいとは思わない?」
ミッチーさんの顔が引きつった。
「東吉野の夜でもハイビームが効かなかったんですよ。ここなら死にますよ」
同感である。
だが、私が知らない巨大な存在に私の好奇心は疼いていた。殺されてみたいと思ったのも事実だ。
後日、ミッチーさんから、あの神社で千日回峰を終えた行者が、信者に祈りを捧げると教えられ、ああ、そうかと思った。
金峰山の仏教は南都六宗とチベット密教ほどに違う。
ここの神仏は我々の常識の埒外なのだ。
ただ拝む者も下界の常人ではいけない。一種の怪物とならねばならないのだ。
私は仏門に入ったと思っていたが、とんでもない間違いだった。
いきなり、眼前に切りたった岩山が現れた気がした。
真の仏門を潜るには、まだまだ未熟な自分を認識した次第である。
※追記
戻る途中、私とミッチーさんは喫茶店で一服を煎れた。
窓際の席で展望が良く、回りの山脈が良く見える。
?
違和感を覚えた。鋭角のふたごぶ山の凹の中央部にあり得ないものが見えた。
ミッチーさんに尋ねる。
「なぁ、あのふたこぶ山の凹んだ所に鳥居が見えない? もしそうなら、三輪の大鳥居を凌ぐ日本一の巨大鳥居だ。方向が鬼門なのも気になる。
「鳥居があるように見えますが、あのあたり人が入れないでしょう」
ミッチーさんはそう答えた。
私は閃いてカメラを超望遠にして覗いた。
日本の杉の大木が枝を絡め合って、自然の鳥居を形取っていた。
「杉の大木だ! それが日本揃って鳥居を形作っているんだ」
そう言うとミッチーさんは、「そんなこと起こりえるでしょうか?」
と疑問を呈した。
あるのだ。
私はかって巨大寺院があった場所が森になっているのが、遠目には寺院にしか見えない形になっているのを経験している。
ドリンクを持って来てくれた定員さんに私は尋ねた。
「あの辺りに宗教施設ありますか?」
店員さんは「人も近づかないけど……、地名は大龍門と言いますね」
質問の意図を汲んだ答えに嬉しくなって、私は言った。
「謎が解けましたね!」